前回
2017.11.5~6
中山道六十九次の宿場の間にある「間の宿」
日本の街道にも良く見られた「日本の心」

旅人への労をネギライうおもてなしは、十分に推察できる
今回のルートも暴れん坊の千曲川の西と東の宿場や
最大の難所・碓氷峠の西の入り口の沓掛や軽井沢宿 

動画編



平安時代からこの地を収めていた豪族望月氏の姓や、その望月氏が朝廷や幕府に献上していた馬の名産地として蓼科山裾野の「望月の牧」から、「望月」の名が付いたとも言われる。なお、望月氏の由来は、望月の牧からであり、望月の牧の由来は、一族が毎年旧暦8月15日の満月の日(望月)に馬を朝廷や幕府に献上していた為である





正縁寺の先で中山道筋は二車線道路から反れて細い坂道を下ります、下りきった辺りに「塩名田宿お滝通り」の碑が設けられています、此処は昔「瀧大明神社」の境内でケヤキの大木が立ちその下から大量の湧水が流れ出ていたと云います 


江戸期はじめの頃は渡場には河石を橋桁とする渡橋が架けられていましたが水害により橋が流され舟渡となりました、その後明治に入り舟橋会社が設立され舟を繋いでその上に橋を架ける舟橋が架けられます、幾度の水害を考慮して直ぐに造り直せる舟橋としたのです 





塩名田宿が最大に活気を帯びたのは江戸期よりも明治中頃で二人の料理人が
八幡宿より移転して角屋を料亭に新装改築してからでした、それ以後塩名田宿は川魚料理で一躍有名に成りました、もともと交通の要所であったので他の
地域から開業移転する業者も多く志賀銀行や製糸工場などもこの頃に営業をはじめました 


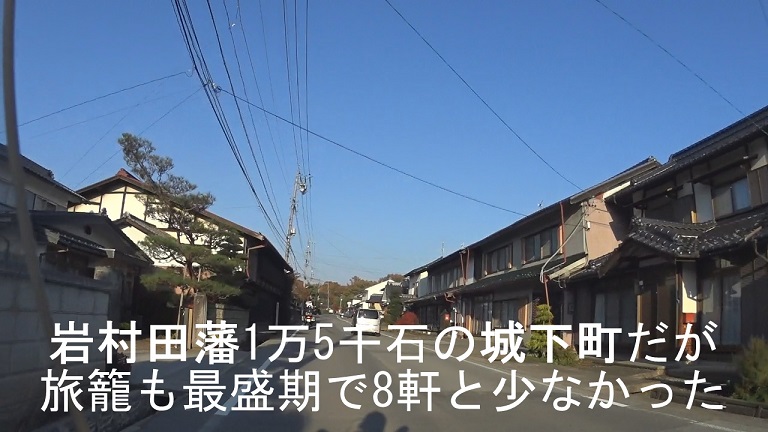



史跡・みどころは多い





この油屋がモデルである 



16:50



毎年、旧車によるラリーを開催しているそうな 


19:15











数百人の飯盛女が働いていたという 宿場の東にある矢ヶ崎川にかかる
二手橋は、旅人と飯盛女が別れを惜しんだ場所 








次回











